📝論文タイトル:Predictive Factors for Pregnancy-Related Persistent Pelvic Girdle Pain (PPGP): A Systematic Review
👩⚕️著者:Burani E, Marruganti S, Giglioni G ほか
📅発表日:2023年12月5日
📚掲載誌:Medicina 2023, 59, 2123
🔗DOI:10.3390/medicina59122123
💬はじめに|産後ママの“あるある悩み”から
👩「出産後、腰や骨盤の痛みがなかなか治らない…」
👱♀️は治ってるのに、なんで私だけ?」
そんな不安を抱えているママ、少なくありません。
実はこの痛み、**妊娠関連骨盤帯痛(PPGP:Pregnancy-Related Pelvic Girdle Pain)**と呼ばれ、産後も慢性化することがあるのです。
今回紹介するのは、PPGPが3ヶ月以上続く女性の特徴(リスク因子)を明らかにしたシステマティックレビューです📚
10本の前向き研究を分析した、信頼性の高い内容になっています。
🔎PPGPってどんな症状?
PPGPとは、妊娠中または出産後に感じる骨盤周辺の痛みのこと。
特に**お尻のあたり(仙腸関節付近)**に痛みが出やすく、太ももの裏まで響くこともあります。
発症は、妊娠初期~出産後1ヶ月以内が多く、多くの人は6週間以内に回復しますが、約3人に1人は3ヶ月以上続き、8.5%の人が2年後も痛みが残ると言われています。
📌この研究の目的と方法
目的:PPGPが長引く女性に共通する“予測因子”を明らかにすること。
対象:妊娠中または出産直後にPPGPがあった女性。
追跡期間:産後3ヶ月〜12年まで(研究により異なる)
分析対象:10本の前向きコホート研究(観察研究)
🚨これが要注意!PPGPが長引く6つのリスク因子
調査の結果、以下の6つが特にPPGPの持続と関連が強いとわかりました👇
① 妊娠中の痛みが強かった(VASスコアが高い)
- 痛みの強さ(Visual Analog Scale:VAS)が6以上だった人は、産後も痛みが残る傾向
- オッズ比(OR)1.6〜2.0
👉痛みが強い人ほど慢性化しやすい
OR(オッズ比):ある要因がある人とない人で、病気がどれくらい起こりやすいかを示す指標
→ 例:OR=2.0 → リスク2倍!
② 誘発テストで陽性が多かった
- 骨盤周囲の圧痛・動作テスト(例:P4テスト、ASLRなど)で6〜16個以上陽性
- OR:3.5〜10.7
👉臨床でチェックできる指標なので、妊娠中の検査で予測可能!
③ 妊娠前から腰痛があった
- 妊娠前や妊娠初期から腰痛や骨盤痛があった人は要注意
- OR:2.4〜4.4
👉再発や慢性化リスクが高い傾向
④ 妊娠中の「生活障害度」が高かった
- 日常生活に支障が出るほどの不便さ(ODI、DRIなど)
- OR:5.2、HR:2.1
👉痛み+動きづらさがあるとリスク増!
※HR=ハザード比(回復スピードへの影響)
⑤ 「痛みを恐れて動けない」思考(FABQスコアが高い)
- FABQ(Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire)=痛みを避けようとしすぎる考え方
- OR:1.06(数値は小さいが、重要な心理因子)
👉動かないことで筋力や機能が落ち、悪循環に
⑥ 神経質傾向(ネガティブ思考が強め)
- 性格傾向で「神経症的傾向」があると痛みが長引く傾向
- OR:2.03
👉不安を感じやすい人は、PPGPが慢性化しやすい可能性
❓逆に「関連なし」とされたもの
以下は今回のレビューで「長期的なPPGPと明確な関係がない」とされた項目です:
- 出産方法(自然・帝王切開)
- 子どもの性別や体重
- 妊娠回数や既往歴
- 感情的ストレス、睡眠障害
- 腹直筋離開(いわゆる“お腹の割れ目”)
🤖なぜこの研究が信頼できるの?
- 前向き研究×10本を統合したレビューで、エビデンスレベルが高い
- 評価に**QUIPSツール(バイアスリスクの評価基準)**を使用
- 5本は低リスク、5本は中リスクの研究と分類
🧭リハビリ部長のまとめと提案
妊娠・出産を経験したすべての方に言いたいのはこれ👇
💬「痛みが強い・長引いてる」「不安で動けない」
そんな時は、我慢せず専門家(整形外科医・理学療法士など)に相談しましょう!
また、妊娠中からの早期スクリーニングも有効です。
産婦人科や助産師との連携で「予測→予防→対応」のサイクルを作ることがカギです。
⚠️注意点(必読)
この結果は、信頼性の高い文献に基づいていますが、あくまで研究の一例であり、すべての人に当てはまるわけではありません。
ご自身の状態については、必ず医師や専門家にご相談ください。
今日の一歩が、未来の元気をつくります🌱
みんなで健康寿命を延ばしていきましょう!!
それではまた次回!😊

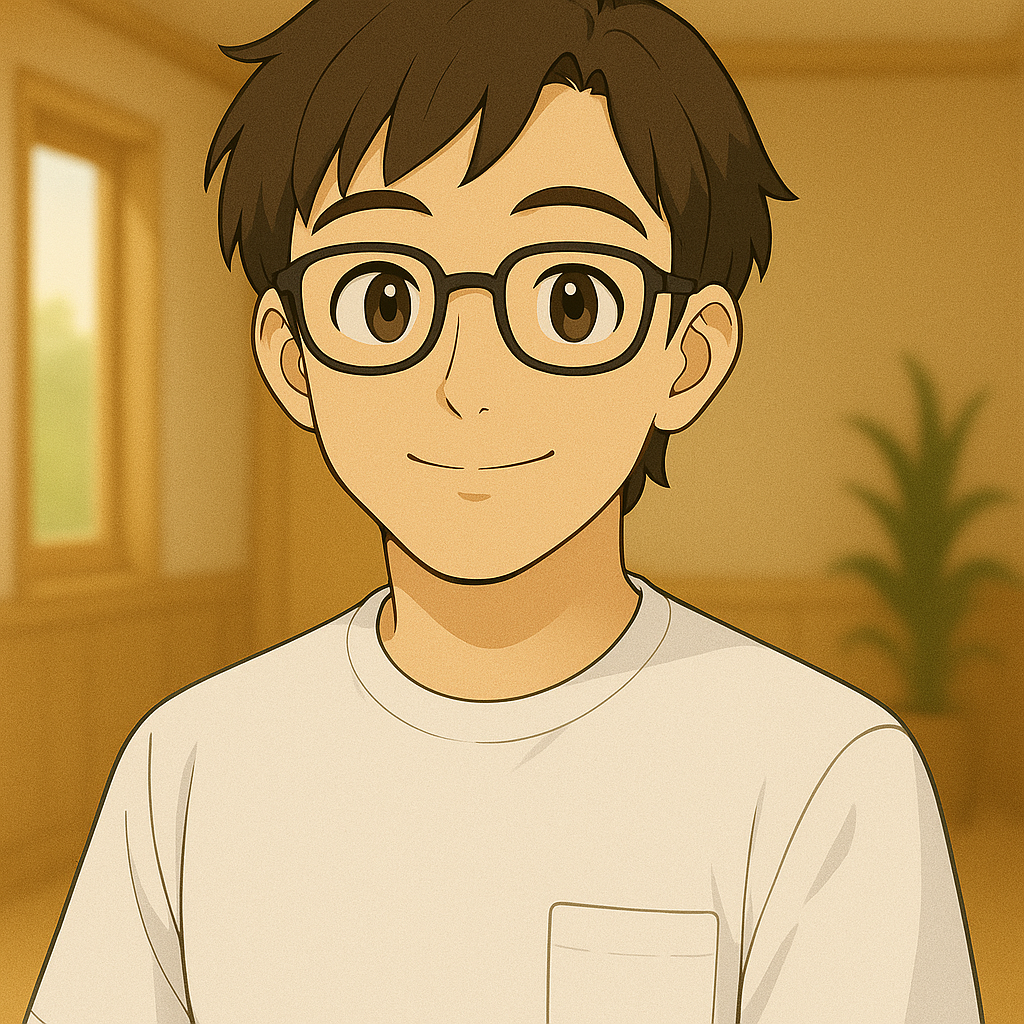
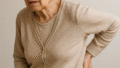

コメント